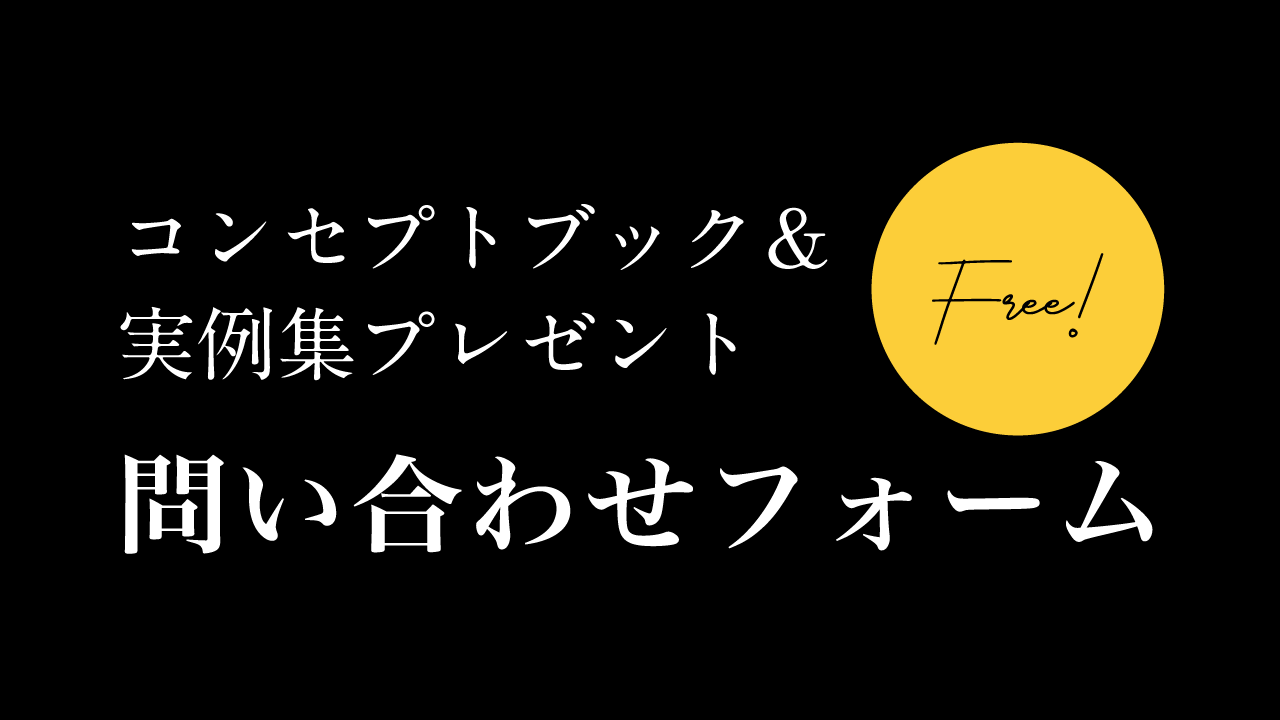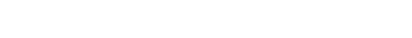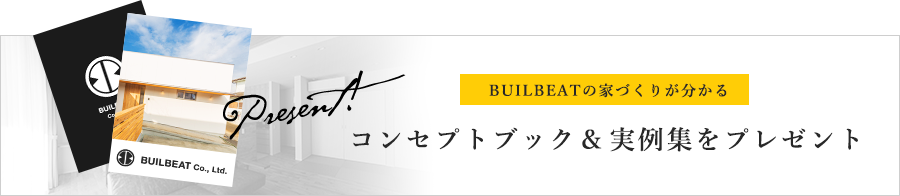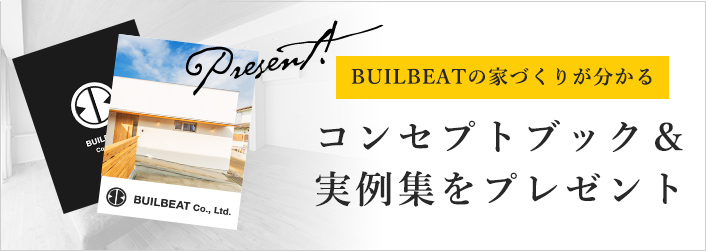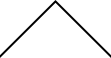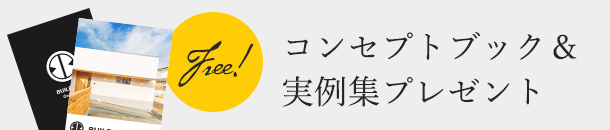【断熱材編】熊本で建築する考え方「裸グラスウール」の性能とメリット

1. 熊本の気候と住まい:なぜ断熱が重要なのか?
熊本特有の気候:夏は蒸し暑く、冬は底冷え
熊本県は九州地方の中央部分にある県です。
基本的には太平洋側気候となっています。
ただ、海も山もあり、さらには平野もある地域ですので特色によって海も山も平野もあるので地域によって少しずつ特徴が異なります。
熊本県の県庁所在地、熊本市では夏は暑く冬は寒い寒暖差の激しい地域です。
出典:熊本地方気象台
断熱材がもたらす快適な室内環境
断熱材が住宅にもたらす影響は非常に多岐にわたり、住む人の快適性、健康、そして住宅自体の寿命や経済性にも大きく関わってきます。
-
室温の安定: 断熱材は外気からの熱の侵入(夏)や、室内からの熱の放出(冬)を防ぎます。これにより、冷暖房に頼りすぎなくても室内の温度を一定に保ちやすくなり、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を実現します。
-
部屋間の温度差の解消: 断熱性能の高い住宅では、リビングだけでなく廊下、トイレ、浴室などの場所でも温度差が少なくなり、家全体が快適な空間になります。これは特に高齢者にとって、ヒートショックのリスクを軽減する上で非常に重要です。
-
防音性の向上: 断熱材には、熱だけでなく音を吸収する効果もあります。また、室内の音が外に漏れにくくなるため、プライバシーの保護にも繋がります。
-
ヒートショックのリスク軽減: 冬場に暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動する際の急激な温度変化は、血圧の変動を引き起こし、心臓発作や脳卒中のリスクを高めます(ヒートショック)。断熱性能を高めることで、家全体の温度差が小さくなり、このリスクを大幅に軽減できます。
-
結露・カビ・ダニの抑制: 断熱性能が低い家では、室内と外気の温度差が大きくなり、壁や窓に結露が発生しやすくなります。結露はカビやダニの発生を促し、アレルギーや喘息などの健康被害の原因となります。適切な断熱材と気密施工は、結露の発生を抑え、クリーンな室内環境を維持するのに役立ちます。
-
室内の空気質の改善: 結露によるカビの発生を抑えることで、室内の空気中にカビの胞子が舞うのを防ぎます。また、高気密・高断熱住宅では計画的な換気システムが導入されることが多く、新鮮な空気を取り入れやすくなります。
出典:SUUMO
光熱費削減と環境負荷低減のメリット

断熱性能の高い家は「魔法瓶」に例えられます。
一度暖めたり冷やしたりした室内の空気を外に逃がしにくく、外の気温の影響も受けにくいため、冷暖房の効率が格段に向上します。
熊本地震後の住宅性能への意識の高まり
熊本地震では、旧耐震基準の住宅に甚大な被害が出た一方で、新耐震基準、特に2000年基準以降の住宅や、住宅性能表示制度の「耐震等級3」を満たす住宅は、倒壊を免れたケースが多かったことが明らかになりました。
裸グラスウールが注目される背景

最も大きな理由は、住宅の「高気密・高断熱化」が家づくりのスタンダードになりつつあることです。
国が推進する「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」のように、少ないエネルギーで快適に暮らせる住宅が求められています。
断熱材は、その内部に閉じ込めた空気が熱の移動を妨げることで性能を発揮します。
しかし、もし壁の中にわずかな隙間でもあれば、そこから空気が対流してしまい、せっかくの断熱効果は台無しになってしまいます。
これは、いくら厚着をしても、服に穴が開いていたら寒いと感じるのと同じです。
裸グラスウールは、袋に包まれていないため、建物の柱や梁の凹凸、配管の裏側など、どんなに複雑な場所でも、現場で細かくカットして手作業で隙間なく充填できます。
この「隙間ゼロ」の施工こそが、断熱材本来の性能を最大限に引き出す上で極めて重要になります。
また、裸グラスウールの場合、別に高性能な防湿・気密シートを施工することが必須です。
一見手間が増えるように思えますが、これにより防湿層と気密層を完全に一体化させ、連続した「防湿・気密ライン」を確立できます。
これは、壁内結露を防ぎ、建物の耐久性を高め、計画的な換気によって室内環境を快適に保つ上で非常に有効です。
高気密・高断熱住宅の実現には、この確実な施工が欠かせません。
出典:マグイゾベール
1. 住宅の高気密・高断熱化の推進
近年、国を挙げて住宅の省エネルギー化が進められています。
特に「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の普及目標など、高い断熱・気密性能を持つ住宅が標準となりつつあります。
-
断熱材本来の性能発揮に不可欠な「隙間ゼロ」施工: 断熱材は、その内部に閉じ込めた空気が熱の移動を妨げることで断熱性能を発揮します。しかし、隙間があるとせっかく閉じ込めた空気が動き、熱が伝わってしまいます。袋入りのグラスウールは、規格化されたサイズで施工がしやすい反面、柱や梁などの凹凸部や配管周りなどで隙間が生じやすいという課題がありました。
-
別張り防湿・気密シートとの組み合わせ: 裸グラスウールは、その名の通り防湿層がないため、別途、高性能な防湿・気密シートを住宅の室内側に隙間なく施工することが必須となります。一見手間が増えるように思えますが、これにより、防湿層と気密層を一体的に、かつ連続して施工できるため、結露の発生リスクを低減し、より確実な気密性能を確保できます。この施工方法が、高気密・高断熱住宅のトレンドとして定着してきたことが、裸グラスウール再評価の大きな要因です。
2. コストパフォーマンスの高さ
他の高性能断熱材(例:硬質ウレタンフォーム、フェノールフォームなど)と比較して、グラスウールはコストパフォーマンスに優れています。
-
安価な材料費: リサイクルガラスを主原料としているため、材料自体のコストが比較的安価です。これは、高性能な断熱材を広範囲に採用したい場合に、総建築コストを抑える上で大きなメリットとなります。
-
高い費用対効果: 断熱性能と価格のバランスが非常に良いため、費用を抑えつつ高い断熱効果を得たいと考える施主や工務店にとって魅力的な選択肢となります。
3. 環境負荷低減への意識の高まり
持続可能な社会への関心の高まりも、裸グラスウールが注目される背景にあります。
-
リサイクル性の高さ: グラスウールの主原料はリサイクルガラスであり、環境に優しいエコ素材として評価されています。
-
長期的な耐久性: 無機質なガラス繊維でできているため、経年劣化が少なく、長期間にわたって安定した断熱性能を維持しやすいという特徴があります。これにより、住宅の長寿命化にも貢献し、建て替えや改修による環境負荷を低減します。
-
不燃性・安全性: ガラスを原料としているため、燃えにくく、万が一の火災時にも有毒ガスを発生しにくいという安全性も評価されています。
2. 「裸グラスウール」とは?その基本と知られざる高性能
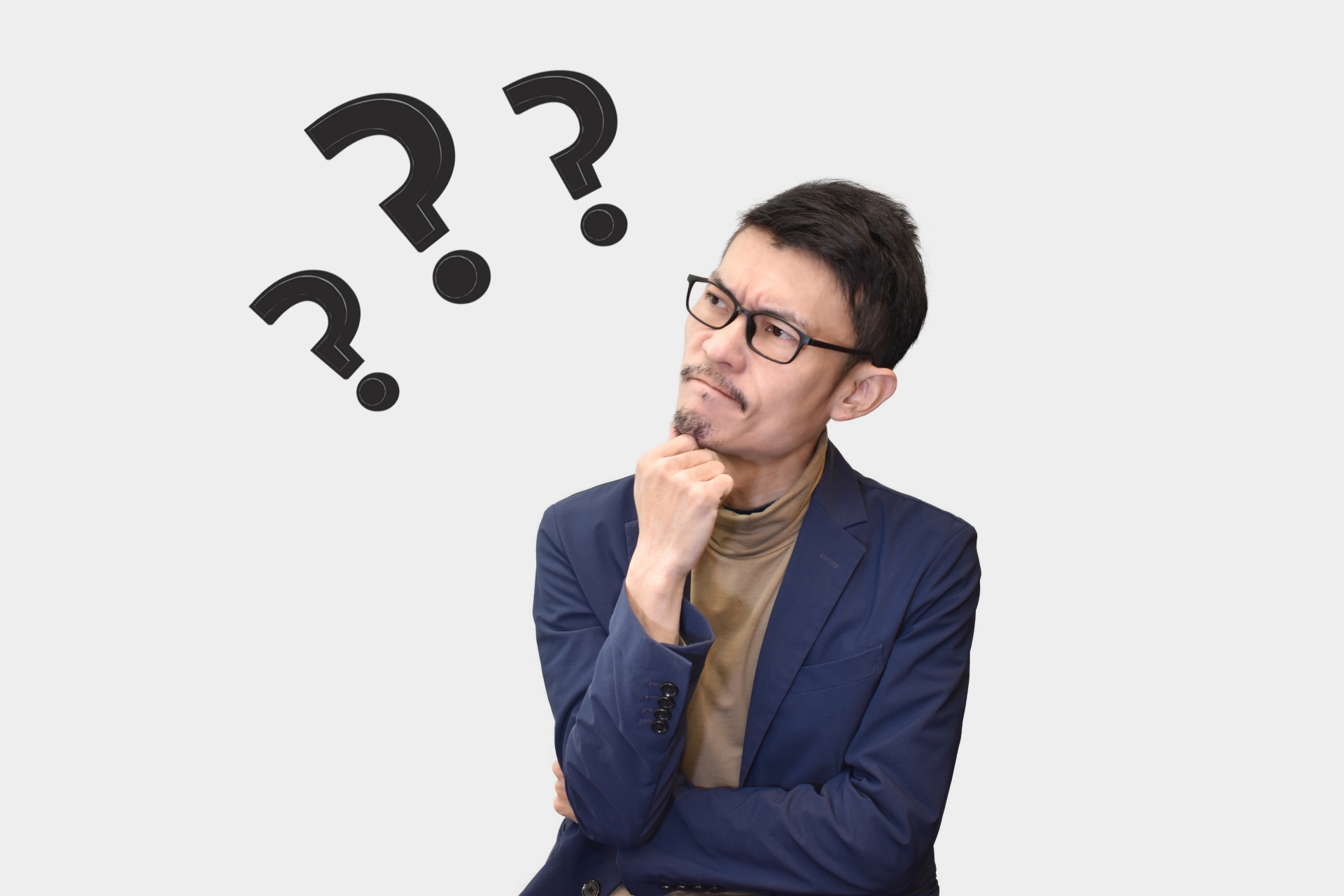
グラスウールの種類と「裸」であることの意味
かつては「袋入り」が主流でしたが、住宅の高性能化が進む現代においては、「隙間なく充填できること」と「確実な防湿・気密層を構築できること」が非常に重要視されるようになりました。
裸グラスウールは、この2つの点を高次元で実現できるため、プロのビルダーや高気密・高断熱住宅を手掛ける工務店から高い評価を受け、その採用が拡大しています。
特に、夏は蒸し暑く冬は冷え込む熊本のような地域では、確実な断熱・気密性能こそが、一年を通して快適で健康的な暮らしを実現する鍵となるため、「裸グラスウール」とその正しい施工は、これからの家づくりにおいて非常に重要な選択肢となるでしょう。
高い断熱性能の秘密:繊維が閉じ込める空気層
どんなに性能の高いグラスウールでも、壁の中にわずかな隙間があれば、そこから空気が対流し、熱が逃げてしまいます。
これは、セーターに穴が開いていると寒く感じるのと同じ原理です。
「裸グラスウール」が注目されるのはまさにこの点です。
袋に包まれていない「裸」の状態だからこそ、柱や梁の複雑な形状、配管周りといった住宅のあらゆる隙間に、職人が手作業でグラスウールを細かくカットし、ぎゅっと押し込むように充填できるのです。
これにより、本来の性能である「繊維が閉じ込める大量の動かない空気層」を最大限に生かし、住宅全体の断熱性能を飛躍的に向上させることができるのです。
低コストで実現するハイクオリティな断熱
「良い断熱材は高い」「ハイクオリティな断熱は費用がかかる」そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「裸グラスウール」は、その常識を覆し、低コストでありながらハイクオリティな断熱性能を実現できる、非常に魅力的な選択肢です。
環境に優しいリサイクル素材としての側面
裸グラスウールは、原料のリサイクル性から製造過程、そして住宅に導入された後の省エネ効果や耐久性まで、多角的に見て環境に優しいサステナブルな建材であると言えるでしょう。熊本でこれからの家づくりを考える際、地球環境への貢献という視点も、裸グラスウールを選ぶ大きな理由の一つとなるはずです。
出典:マグイゾベール