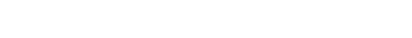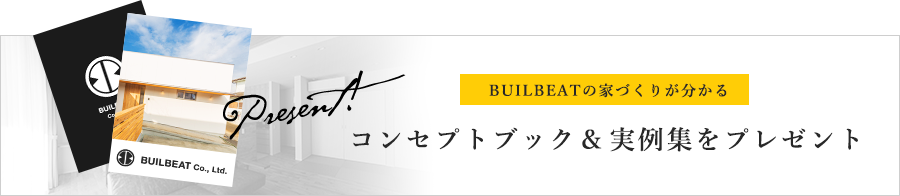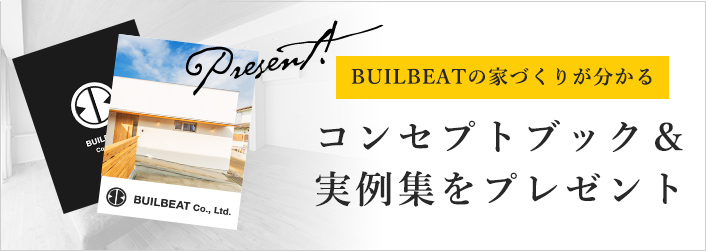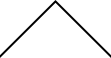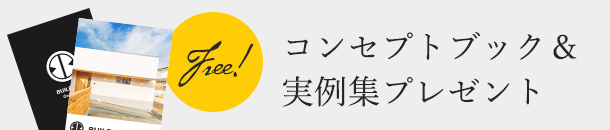建築基準法だけじゃない!設計事務所が考える、安全で快適な家づくりのポイント

はじめに
安全で快適な住まいで暮らしたいとは誰もが願うことです。
安全も快適さも、それぞれ何か一つの要因だけでは決まるものではありませんが、安全性についていえば、地震や台風などの自然災害に強く、健康被害などのリスクを減らせる住宅であること、快適性についていえば、室内で感じる暑さ寒さや空気の質、自然光を取り入れられる設計かどうかということが大切な要因になるでしょう。
そこでこのコラムでは、これから家づくりを始める方に向けて、熊本の設計事務所目線で安全で快適な家づくりのポイントについて解説していきたいと思います。
1.熊本の設計事務所が考える安全な住宅・快適な住宅とは?
・熊本の設計事務所が考える安全な住宅とは
日本は自然災害が多い国です。毎年のように台風や大雨などの被害が各地で発生するだけではなく、大きな地震が発生する確率が高いともいわれていますので、これから住宅を建てるのでしたら、強くて安全な住宅にすることが大切です。
また、警視庁発表のデータによると、近年の全体的な侵入窃盗数は減少傾向にあるものの、件数は依然として多い状況であることから、災害に対する強さとともに、防犯性にも気を配るとより安心して暮らせるでしょう。
住宅は大きな買い物ですから、長く安心して暮らせる家づくりをしたいですね。
出典:すまいる110番
・熊本の設計事務所が考える快適な住宅とは
住まいの快適性に影響を与える要素には、空気環境・暑さ寒さ・明るさ・室内の意匠性・耐震性などがあります。快適な住宅は、このような要素が組み合わさって生まれます。
その中でも、ちょうどよい温熱環境や空気の質は暮らす人の健康にも直接影響を及ぼすため、優先的に考えておきたい要素といえます。
人は、夏は涼しく、冬は暖かい気温を快適だと感じます。気温の目安は夏は27度以下、冬は22度以上です。
さらに、冬に暖かい浴室から寒い脱衣所へ移動する際などに生じる急激な温度変化で、血圧が急変動したり、脈拍が速くなったりします。
これを「ヒートショック」といい、脳卒中や狭心症などを引き起こす危険性もあり、特にご高齢の方には非常に危険です。
住宅の中が外気の影響を受けにくく、家全体の温度が一定に保たれていると、住む人は健康かつ快適に暮らすことができます。これは、家の性能の良さなしでは成立しません。

2.設計事務所が考える、安全で快適な住宅にするために必要なこと
快適な住まいに必要な住宅性能は「断熱性」「気密性」「換気」の3つです。
また、安全に暮らしていくためには、「ハザードマップで住んでいる土地を確認する」「耐震等級」「防犯」に気をつけておくとよいでしょう。
・断熱性
断熱性とは、家と外の熱をどのくらい通しにくいかを表す性能のことです。
断熱性が優れた家は、夏は外の暑い空気を伝えにくく、家の中の涼しい空気を外に逃がさず、冬は外の冷たい空気を伝えにくく、家の中の暖かい空気を外に逃がさないため、「夏は涼しく、冬は暖かい家」にすることができるようになります。
・気密性
気密は、建物にある隙間の大きさがどれくらいかを表す指標です。意識が高い施工会社ですと、わざわざ検査をして値を調べますので、「御社で建てた建物のC値はどれくらいですか?」と尋ねてみるのもよいかもしれません。
気密性が高いというのは、家にある隙間が小さいということです。そのため、家に隙間が多いほど夏は暑い外の空気が家の中に入りこんでしまい、冬は冷たい空気が家の中に入ってきてしまうことは、イメージがしやすいと思います。
つまり、いくら断熱性能が良い家でも、気密性が高くなければ意味がなくなります。
また、気密性が高いほど、余分な隙間から空気が入ってこないせいで室内の24時間換気がうまく機能しやすく、家全体の空気が計画通りに流れます。そのため、結露やカビ・ダニが発生しにくく、アレルギーの方は特に暮らしやすくなるでしょう。
筆者の経験でも、高気密・高断熱の住宅に引っ越したお施主様のアレルギー症状がおさまり、快適に眠ることができるようになったという事例があります。
・換気
換気は家から出た空気の量と同じだけ、外からの空気が家に入ってきます。
そのため先にも述べた通り、隙間が多い家では、せっかく快適な温度になっている家の中の空気を外に捨て、外からの不快な温度の空気を家の中に入れてしまいますので、たいへん光熱費の負担が増えます。
また、換気は換気システムを通じて、家全体の空気の流れをデザインし、効率良く、無駄なく行われなければなりません。換気口は開けた状態で24時間換気システムは常に稼働させ、正しい換気を行うことが重要です。
以上のように、断熱・気密・換気の3つの性能は住宅の快適さに密接にかかわりあっており、どれが欠けてもいけません。3つとも高い水準を維持している必要があります。
いずれも非常に重要なことですので、家づくりの際にはぜひ参考にしてください。
・ハザードマップを確認する
先述のように、日本は災害が多い国です。毎年のようにどこかで水害が起きており、熊本も例外ではありません。住宅を建てる際には、必ず市町村のハザードマップを確認しましょう。
参考:熊本市ハザードマップ
・耐震等級3をとる
日本は地震が多い場所に位置しています。
熊本でも2016年に熊本地震が発生し、かつて誰も想定していなかった2度にわたる震度7の揺れを受けて大きな被害が出ました。そんな熊本地震でたいした被害がなかった住宅の共通点は、耐震等級3であったことです。
耐震等級は、建物の耐震性を表す指標であり、以下のように数字が大きくなるにつれて強度が高い家になります。
・耐震等級1級:建築基準法によって定められた耐震基準
・耐震等級2級:耐震等級1級の1.25倍相当の強度
・耐震等級3級:耐震等級1級の1.5倍相当の強度
熊本でも、まだ断層の南部には地震のエネルギーが残っているといわれています。
これから住宅を計画するのでしたら、ぜひ耐震等級3をご検討ください。
・防犯性を上げる
次に、防犯性の高い家をつくるための条件について説明します。ポイントは次の二点です。
①狙われにくい家づくり、狙われやすい部分の防犯性を強化
②ご近所との連携をとる
①の「狙われにくい家づくり」とは、まずは泥棒に目をつけられにくい家にしようということです。例えば家の周囲を高い塀や植栽で隠してしまい、敷地内の視線を遮られた家は、侵入後に人目につかなくなるため、泥棒にとっては好都合な作りの家となります。さらに、泥棒に狙われやすい開口部の防犯性を強化しましょう。泥棒に狙われやすい場所とは、道路や周囲の家から見えにくい部分です。体が通らないような小さな窓は侵入経路から外れるので、シャッターや面格子をつけたくない場合などはそのような小窓を多用するのも一つの方法です。シャッターや面格子、玄関ドアには、特に防犯性に優れた商品も出回っており、目印に「CPマーク」がついています。気になる方は、これらを採用することで防犯性を上げることが期待できます。
②「ご近所との連携」
住宅に直接関係はありませんが、番外編として説明しますと、泥棒が一番嫌うのは「人目」です。多くの泥棒は狙った家の下見をするといいますが、ご近所同士の連携が取れている地域では不審者が紛れ込んでもわかりやすく、声かけを行うことで泥棒が犯行を諦める可能性が高くなります。また、このような近隣同士の連携は防犯に効果を発揮するだけではなく、災害時にも皆で乗り切る力になることもありますので、良好な近隣関係が築けると良いですね。

まとめ
いかがでしたか。
以上のように、安全かつ快適な家づくりをするにはいくつかのポイントがあります。
熊本の設計事務所目線で解説をしてみましたので、これから家づくりを始めたいと考えていらっしゃる方の参考にしていただけますと幸いです。