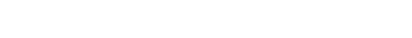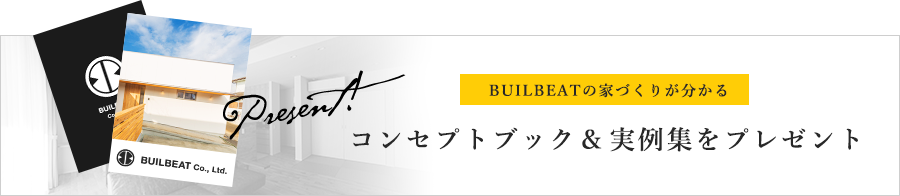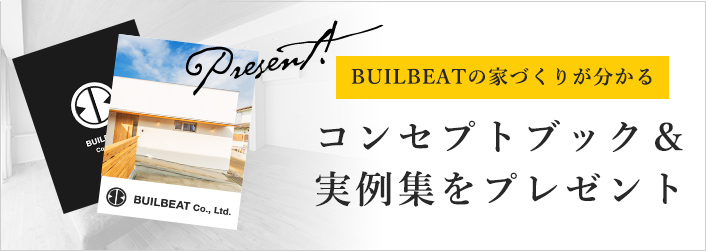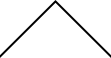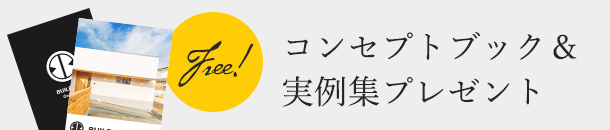「この土地、大丈夫?」設計士が教える、見落としがちな土地のチェックポイント

はじめに
そろそろ注文住宅をと考えている方たちは、どのように土地を選べばよいのかという点も気になることでしょう。
せっかく選んだ土地が理想の家を建てることができない要素を持っていたとしたら、残念な気持ちになるかもしれませんよね。
それでは、設計士は家の設計をする時、土地のどんなところに注目しているのでしょうか。また、
一般の人との違いはあるのでしょうか。
このコラムでは、設計士は土地のどんな点をチェックしているのかについて見ていきたいと思います。
一般的に土地選びで重視されているもの
まずは、一般の方たちが土地を選ぶ際に重視しようと思っていること、家を建てたときに重視したことをみてみましょう。大和ハウスさんのアンケートによると、土地選びにおいては大きく分けて次のような項目が重要視されているようです。
1.利便性
突出して多いのが「日常での買い物等の利便性」(69%)で、次に「通勤の利便性」(39%)が続くという結果でした。やはり、その土地で生活を継続すると考えると、利便性は重要
度が高いということなのでしょう。
2.周辺環境
具体的には、「近隣の環境が自身に合ったものであるかどうか」(32%)、「子育てや教育にとって有利な環境であるかどうか」(21%)、「自治体サービスの充実度」(17%)、「自然の豊かさ」(21%)という項目があがっていました。いずれも、その地域の周辺環境を重視していることが推察できます。
3.建物の建築を意識
具体的には、「ご自身が希望する建物が建てられるかどうか」(8%)、「土地の広さや形状」(23%)、「日当たりや風通しの良さ」(30%)という項目があがっていました。これらの回答からは、住宅の建築をする段階をイメージして土地探しをしておられことが見て取れます。

設計士が住宅をプランするときに見ている土地のポイントは?
それでは、ここから先は住宅を設計する設計士が土地のどのような点を見ているかについて見ていきましょう。
① 法規制
場所によっては、建物の用途や規模、高さなどに制限が定められていて、建設が許可されない土地もあります。そもそも希望の家を建てることができるのかどうかにかかわる部分で、例をあげると次のようなものがあります。
・建ぺい率・容積率
建ぺい率とは、土地の面積に対する建物の建築面積の割合です。 容積率とは、土地の面積に対する延べ床面積の割合を指します。
・用途地域
どのような建物を建てることができるかどうかにかかわる地域区分になります。上記の建ぺい率や容積率にも影響します。
・道路・斜線制限
周辺の環境(採光、通風、圧迫感など)を保護するために、建築物の高さを制限する建築基準法の規制です。道路や隣地からの距離に応じて、建物の高さや形状を制限します。
・防火地域や調整区域 など
防火系の地域であれば建てられる建物の構造や材料などに制限があったり、調整区域であれば住宅を建てることができないなどの制限にかかわったりもするので、これも大切なチェックポイントです。
② 接道状況や前面道路など
道路は、土地に接している幅が規定より少ないとそもそも住宅を建てることができなかったり、セットバックして住宅を建てる必要がある場所では思ったよりも住宅を建てられる面積が少ないということもあります。
具体的なチェックポイントの例は次のようなものとなります。
・接道義務を満たすか
・前面道路の幅は?
・道路が私道なら、権利関係は?
③ 前面道路の幅やインフラ
前面道路の幅員や上下水道の整備状況などのインフラも、合わせて確認しておきましょう。これがあとで大きなコスト増につながることもあるためです。
具体的なチェックポイントの例は次のようなものです。
・上下水道、電気・ガスの引込状況
・排水処理や雨水マスの整備状態
④ 高低差がある土地
・傾斜地・擁壁のリスクがあることも知っておこう
傾斜地とは、平坦ではなく傾斜している土地のことです。角度の明確な定義があるわけではありません。傾斜地は、平坦な土地よりも価格が安く、眺望が良いなどのメリットもありますが、擁壁や造成工事が必要で予想外のコストがかかってしまったり、地盤が弱いと地震に弱いなどのデメリットもあります。
擁壁のリスクは、老朽化による崩壊、排水不良による土砂災害、地震による倒壊など、多岐にわたります。特に古い擁壁や、建築基準法に適合していない擁壁は、災害時に重大な危険を伴う可能性がある点に注意が必要です。
⑤ 周辺環境の中の災害リスクをチェックしてみる
住宅に向いている土地かどうか、周辺地域の状況も含めたさまざまな観点から総合的に調査しましょう。 そこだけ見ると理想に近い土地であったとしても、土砂崩れや水害のリスクが高いということもあるかもしれません。
県や市区町村では、液状化、水害や土砂災害のリスクがある地域を公表しています。 自治体のホームページでハザードマップを確認し、国土地理院のホームページで地形分類図や過去の航空写真もチェックしておくのがおすすめです。
埋め立てによって造られた土地であったり、以前に河川が流れていた土地、河川のそばなど、土地の経歴や変遷を把握しておけば、災害リスクを低減することができます。
また、以前に工場があった土地などでは、場合よっては土壌が汚染されている可能性もあるため、もし気になれば事前に調べておくと安心でしょう。
さらに、地域に電力を供給する高圧線が上空を横切っている場合、その下は建築制限がかかっている可能性が高いです。 敷地の真上を横切っていない場合でも規制されているケースもありますので、気になっている土地の周辺に高圧線があった場合は、所轄の電力会社で確認しておきましょう。
⑥ 実際の周辺環境で見落としやすい点をチェックしよう
周辺環境の見落としやすい点を実際に確認しておくのはおすすめです。具体例としては次のようなものがあります。
・騒音・異臭の有無があるかどうか
・近隣の土地の建物の高さや日当たり
・ごみ置き場、墓地など
参考コラム:設計事務所が解説!熊本で注意すべき土地の特徴と構造設計のポイント
出典:日本擁壁保証協会

そもそも、家を建てられない土地はあるのか?
そもそも、家を建てられない土地があるかないかといえば、あるというのが答えです。
家を建てられない土地の種類を次にまとめていますので、これも土地選びの参考にしていただければと思います。
1.市街化調整区域の土地
2.接道義務を満たしていない土地
3.農地転用していない土地
4.再建築不可物件を解体した土地
(現在の建物を解体すると、新たに建物を建てることができない土地)
5.傾斜角度15°以上の傾斜地
6.安全性の確認ができない擁壁がある土地
7.高圧線下にある土地
参考:土地カツnet
土地選びで実践すべきその他3つのこと
また、きちんと情報を集めても、それだけでは気づくのが難しいこともあります。
購入前に、次にご紹介する3つをやってみることをおすすめします。
1.時間帯を変えて土地を見に行く
朝・昼・夜、平日・休日で変わる場所の空気感を見に行ってみましょう。
2.周辺を歩く
道、雰囲気、交通量など、実際に行ってみないと分からないこともあります。
可能ならば通勤・通学時のタイミングで行ってみることもおすすめです。
3.建築会社に一緒に見てもらう
プランの仮検討ができると、買ったあとに後悔する要素を減らすことができるでしょう。
まとめ
周辺の交通量や利便性、日照や風通し、自然環境や価格など、すべてが満足する土地に出会うのは難しいものです。
しかし、立地条件の多少の制約などは設計の工夫次第で、住みやすい家を実現できたり、理想の家に近づけたりできる可能性もあります。
その一方で、立地や眺望、利便性が優れているからと土地を購入してしまうと、建築費に無理が生じ、理想の家づくりが難しくなる可能性があるのも事実。
よって理想の実現には、これからの生活やライフプラン、住む場所や家のイメージの具体化が必要です。気になる土地が出てきたら、購入前に住宅会社やお願いしたい建築家に相談してみると、より理想の実現に近づく可能性が高まるでしょう。